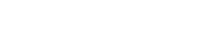2.沖縄のお墓と本土のお墓
お墓の大きさ
本土から訪れる方々がまず驚かれるのは、沖縄のお墓の大きさです。至る所にあるお墓を見て公衆トイレと間違える方もおりました。本土では考えられない大きさなのです。このお墓の大きさが、まずは沖縄と本土との大きな違いです。本土では1㎡(1m×1m)の敷地に高さ約150㎝が一般的な大きさなのに対して沖縄では3坪(約10㎡)の敷地に高さ2m以上のお墓が主流で、お墓の前にはある程度の広さの墓庭があります。
4月の清明祭(シーミー)の時期になると、この墓庭にテントやブルーシートが広げられ、車座になった家族や親せきがまるでピクニックのように会食を行います。このようにお墓は親戚との交流の場としても重要な場所となっております。
「家」のようなお墓
このようにお墓の形が大きく異なっているのは、沖縄のお墓が中国の影響を受けていることもありますが、納骨の方法が異なることもその一因と考えられます。
沖縄では、故人のお骨を平均7寸(直径21cm)サイズの骨壺に納め、そのまま地上納骨します。そのため、どうしても納骨室が必要になり、家族の所帯に応じた大きな部屋が必要になります。
内部を覗いたことあるかも知れませんが、中は三段のひな壇になっております。目上の方から順番に上段から下段に安置するようになっております。
門中墓では、さらに大きな部屋になりますが、納骨室の奥に合葬する箇所(カロート)が設けてあります。人数が増えても大丈夫なように、合祀できるようになっております。最近のお墓では、家族墓でも、骨壺を安置するひな壇の下に、このようなカロートを設けるようになっております。33回忌を終えた方は、成仏したとのことで、このカロートへ合葬されます。
それに対し本土では、地域にもよりますが、お骨は骨壺のまま安置せずに、さらし(白い布)で包んでカロートという地下納骨室に安置されます。お骨は土に返ったとの解釈です。地上納骨用の部屋が無い分、お墓もコンパクトになっております。
また、沖縄のお墓は、まさしく「家」のような屋根付きのお墓が主流なのに対して、本土では四角い墓石を積み上げ、一番上に「〇〇〇家之墓」と家族の名前が彫刻された墓標が乗ります。お墓参りをするときは、沖縄では扉に向かって手を合わせますが、本土ではその彫刻された墓標に向かって手を合わせます。
全くの異文化に感じますが、ここ最近では霊園の普及で両者の主な特徴をとらえた霊園型のお墓も多く見られるようになってきました。時代の変化と共にお墓の形も少しずつ変わってきております。