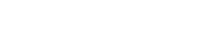3.沖縄のお墓の歴史
お墓の変遷
沖縄でお墓と言えば亀甲墓(カメコウバカ)が有名ですが、沖縄のお墓の一番古い形は、洞窟や岩陰などに遺体をそのまま葬った風葬という形です。やがて周りを石積みするようなり、人工的に手を加えて、堀を大きくし、屋根を付けるようになってきました。
そのような経緯で進化したのが、「破風墓」(ハフウバカ)と呼ばれる家型のお墓です。首里の王家の墓で有名な玉陵(タマウドゥン)がこの破風墓です。また、糸満市にある「幸地腹門中墓」も有名です。
これらの古い墓が岸壁を背にしている大きな墓であるのに対して、現在個人墓の多くは平地に建てられた家形のこじんまりした破風墓で、「ヤーグァーバカ」とも呼ばれております。
亀甲墓は時代的に古いものではなく、お墓の歴史から言うと意外に新しい形です。その外見が亀甲の形をしており、「かめこうばか」、あるいは「きっこうばか」と呼ばれます。この独特な形は女性の子宮をかたどった「母体回帰」の思想に基づくという説もございます。この亀甲墓で最も古いのは那覇市首里石嶺町にある伊江御殿のお墓(1685年築造)と言われております。琉球王府時代には庶民が墓を造るのは禁止されていたので、一般に広く流行したのは明治中頃以後のことです。
お墓の形態
沖縄のお墓には村墓、門中墓、家族墓などがございます。「村墓」は村落の共同の墓で現在ではほとんど見られません。「模合墓」は知人、友人などが共同で所有する墓で「寄合墓」ともいいます。「門中墓」は門中と呼ばれる父系親族の共同墓地で、沖縄本島南部に比較的多く、清明祭などお墓の行事の際には大きなお墓に親戚一同が集まります。その他にも兄弟で所有する「兄弟墓」や家族で所有する「家族墓」がございます。この家族墓は那覇市を中心に広がり、近年最も多く建てられている形態です。
個人でお墓を造るようになったのは、土地整理法(1903年)以後のことです。沖縄の墓は海辺の村では海に向かって建てられていることが多く、集落からは少し離れたところに造られておりました。
お墓の歴史に多く関わってきますが、埋蔵の方法にも移り変わりがございます。昔は火葬が行われず、洞窟や墓の中に安置し数年で白骨化させ、その後洗い清めて改葬する儀礼が行われておりました。
共同使用の大きなお墓の中には、遺骨を白骨化させる場所(シルヒラシ)があり、新しく死者が出た場合、墓口に近い砂利敷きの場所に棺箱を安置したといわれます。そのため門中墓などでは、シルヒラシ用に墓内に広い場所が設けられておりました。
現在は死後すぐに火葬が行われ、お墓に遺骨を納骨しますので、棺桶を安置することが無くなり、以前ほど広いお墓の必要は無くなっております。